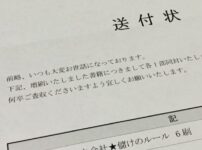最高!本田宗一郎の肉声1分スピーチ。宗一郎と対立疾走した3代目久米社長に「ええかげんなのがウチの社長になるんや!」まさにオヤジ!超実力技術者+この人柄だから、創業期のヤマハ発動機を親切指導逸話は一番下に
■Wiki1906年(明治39年) - 11月17日、静岡県磐田郡光明村(現・浜松市天竜区)で鍛冶屋をしていた本田儀平と妻・みかの長男として生まれる。
1913年(大正2年) - 光明村立山東尋常小学校(現・浜松市立光明小学校)に入学。在校中に自動車を初めて見る。アート・スミスの曲芸飛行を見学するため、遠く離れた浜松町和地山練兵場まで自転車を三角乗り[1][2][3]で訪れ、飛行機を初めて見るなどの経験をする。
1919年(大正8年) - 二俣町立二俣尋常高等小学校(現・浜松市立二俣小学校)入学。
1922年(大正11年) - 高等小学校卒業、東京市本郷区湯島(現・東京都文京区湯島)の自動車修理工場「アート商会」(現在のアート金属工業[1])に入社(当時の表現で「丁稚奉公」)。半年間は、社長の子供の子守りばかりであった。
1928年(昭和3年) - アート商会に6年勤務後、のれん分けのかたちで浜松市に支店を設立して独立。宗一郎ただ1人だけが社長の榊原郁三からのれん分けを許された。
1935年(昭和10年) - 小学校教員の磯部さちと結婚。
1936年(昭和11年) - 第1回全国自動車競走大会(多摩川スピードウェイ)に、フォードに自作のターボチャージャーをつけたマシン[4]で弟の弁二郎[5]とともに出場するが事故により負傷、リタイアを喫する。
1937年(昭和12年) - 自動車修理工場事業を順調に拡大、「東海精機重工業株式会社」(現・東海精機[2]株式会社)の社長に就任。エンジンに欠くべからざる部品としてピストンリングに目をつけるが、経験からだけではどうにもならない学問的な壁に突き当たり、浜松高等工業学校(現・静岡大学工学部)機械科の聴講生となり、3年間金属工学の研究に費やす。
1939年(昭和14年) - アート商会浜松支店[6]を従業員の川島末男に譲渡し、東海精機重工業の経営に専念する。
1942年(昭和17年) - 長男・博俊(元「無限」代表取締役)誕生。豊田自動織機が東海精機重工業に出資、自らは専務に退く。
1945年(昭和20年) - 三河地震により東海精機重工業浜松工場が倒壊。所有していた東海精機重工業の全株を豊田自動織機に売却して退社、「人間休業」と称して1年間の休養に入る。
1946年(昭和21年) - 10月、浜松市に本田技術研究所 (旧)設立。39歳の宗一郎は所長に就任。
1948年(昭和23年) - 二男・勝久誕生。本田技研工業株式会社を浜松に設立。同社代表取締役就任。資本金100万、従業員20人でスタート。二輪車の研究を始める。
1949年(昭和24年) - のちにホンダの副社長となる藤沢武夫と出会い、ともにホンダを世界的な大企業に育て上げる。ホンダの社史については本田技研工業#社史の項目を参照
1961年(昭和36年) - 藤沢とともに「作行会」という財団法人を設立。若手研究者や学生に対して匿名で奨学金を交付[7]した。
1973年(昭和48年) - 中華人民共和国を訪れた帰国直後の会見で、本田技研工業社長を退き、取締役最高顧問に就任することを発表。研究所所長は続けた。
1981年(昭和56年) - 勲一等瑞宝章を受章。
1983年(昭和58年) - 取締役も退き、終身最高顧問となる。
1989年(平成元年)- アジア人初のアメリカ合衆国の自動車殿堂入りを果たす。
1991年(平成3年) - 8月5日、東京・順天堂大学医学部附属順天堂医院で肝不全のため死去。84歳没。葬儀は宗一郎の遺言通り、葬儀は家族で静かに送られた。同日、正三位・勲一等旭日大綬章贈位。
2010年(平成22年) - 4月1日、出生地である静岡県浜松市天竜区に本田宗一郎ものづくり伝承館がオープン。建物は国の登録有形文化財(建造物)に登録されている旧二俣町役場を改装したものである。
■エピソード 編集
詳細
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。
終戦直後は何も事業をせず、土地や株を売却した資金で合成酒を作ったり、製塩機を作って海水から塩を作り米と交換したりして「遊んで」いたという。しかしこの時期に、苦労して買い出しをしていた妻の自転車に「エンジンをつけたら買い出しが楽になる」と思いつき、オートバイ研究が始まる[8]。
会社のハンコを藤沢武夫に預け、経営もすべて任せていた。本田は社印も実印も見たことがなく[9]、技術部門に集中し、のちに「藤沢がいなかったら会社はとっくのとうに潰れていた」と述べており、藤沢も「本田がいなければここまで会社は大きくならなかった」と述べている[10]。互いに「西落合」(本田の自宅のある地)、「六本木」(藤沢の自宅のある地)とざっくばらんに呼び合っていた。また両者は「会社は個人の持ち物ではない」という考えをもっており身内を入社させなかった[11]。宗一郎は社名に個人の姓を付したことも後悔もしていた。
経営難に陥ったときに藤沢の助言でマン島TTレースやF1などの世界のビッグレースに参戦することを宣言し、従業員の士気高揚を図ることで経営を立て直した。出場宣言は藤沢によって書かれた[12]。
藤沢の死後、1989年に本田宗一郎が日本人として初めてアメリカの自動車殿堂入りを果たしたときに、本田は授賞式を終えて帰国したその足で藤沢邸に向かい、藤沢の位牌に受賞したメダルを架け「これは俺がもらったんじゃねえ。お前さんと二人でもらったんだ。これは二人のものだ」と語りかけた[13]。
従業員からは親しみをこめて「オヤジさん」と呼ばれていたが、一方でともに仕事をした従業員は共通して「オヤジさんは怖かった」とも述べている。作業中に中途半端な仕事をしたときなどは怒声と同時に容赦なく工具で頭を殴ったり、実験室で算出されたデータを滔滔と読み上げる社員に業を煮やし「実際に走行させたデータを持ってこい」と激怒して灰皿で殴ったりしていた。しかし、殴られたはずの者よりも、殴った宗一郎の方が泣いていたということもあったという。また怒る際、「人はよく、かわいいからこそ怒るなんて言うが、おれはそうじゃない。そのときはほんとに憎たらしくなる。なぜなら、おれたちのつくる商品は人命にかかわるものなんだ。それをないがしろにする人間は絶対に許せない」と言ったとされる。[14]
南青山の本社ビルを新築する際、「万が一地震が起こったときに割れたガラスが歩道を歩く人に降りかからないようにしなさい」と指示し全フロアにバルコニーがつけられたという。また藤沢もまったく同じ指摘をしていたという。ちなみにビルの設計は、初代シビックのイメージに基づかれていたという。
皇居での勲一等瑞宝章親授式へ出席の際、「技術者の正装とは真っ白なツナギ(作業着)だ」と言いその服装で出席しようとしたが、さすがに周囲に止められ最終的には社員が持っていた燕尾服で出席した。本人曰く燕尾服を持っていなかったためそのような発言をしたとのことである[15]。
無類の鮎の友釣り好きで、年に一度は多数の客を自宅に招き、鮎を放った小川で「鮎釣りパーティー」を行っていた。
大の別荘嫌いで「1年のうちに1週間から10日しか住まない所に金をかけるなんて実にばからしい」と言い、生涯所有はしなかった。
差別を「諸悪の根源」とし、差別を徹底して嫌っていた。子どものころに「家族の中でお風呂に入る順番が決まっている」ことに気づいてからだという。「人種や家柄や学歴などで人間を判断することを、私は今日まで、徹底してやらなかった」[16]
三重県で開かれたある会議に参加した本田は、管理職の1人が松阪牛の料理店・和田金での昼食を提案したところ、「50人も一緒に食事できる部屋はあるのか」と問い、一部管理職以外の参加者が弁当を食べることを知ると、自分も弁当にすると言った[17][18][19]。
邱永漢・渡部昇一『アジア共円圏の時代』によると、作家・経済評論家の邱永漢に、ホンダの海外の工場で一番うまくいっているところと一番具合が悪かったところを問われた本田は「いいほうを『台湾』、悪いほうを『韓国』」と答えたという。韓国について、「『どうしてですか?』と尋ねると、『向こうへ行って、オートバイを作るのを教えた。それで、一通りできるようになったら、『株を全部買いますから、帰ってくれ』と言われた。『どうしましょうか』と下の者が聞いてきたから、『そんなことを言われるところでやることはねえよ』と言って、金を返してもらった。その翌日に朴正煕が殺されたんだ』とおっしゃった」という[20]。なお、本田がオートバイを作るのを教えたとされる台湾および韓国のメーカーは本書では明らかにされていない。ちなみに朴正煕が殺された1979年当時、ホンダが韓国で提携していたのは起亜技研(起亜グループの二輪車部門)であり、実際にホンダは1975年より続いた起亜技研との合弁事業を1979年に解消して資本撤退している[21]が、一方で技術供与は継続しており、起亜のバイクが「KIA Honda」ブランドで販売されていた。また、1981年に起亜技研が大林グループ入りして大林自動車となった際には大林自動車にも技術供与を行い、大林のバイクが「DAELIM Honda」ブランドで販売されていた[22][23]。ホンダが起亜に「帰ってくれ」と言われたのが事実かどうかは不明だが、少なくとも起亜技研・大林自動車とは合弁解消以後も良好な関係を持っており、ホンダが起亜と提携した1975年以降で「Honda」ブランドが韓国から撤退したことはない。
また、「韓国側は、本田とのライセンス契約を一方的に解消し、エンジンからデザインまでまったくのコピー品を『韓国ブランド』として販売を始め、宗一郎は周囲に『韓国とは絶対に関わるな』と言いつけた」と言うエピソードがネット上で流布しているが、ソースが不明であるうえに、本田の存命中に起亜および大林がホンダとの提携を解消したことはなく、事実に反する。なお、ホンダとの提携を解消する2000年代以前の大林のバイクはエンジンからデザインまでホンダのまったくのコピー品が多いが、当然ながらライセンス契約を結んで正式に技術供与を受けているからであり、車体には「HONDA」と「Daelim」双方のエンブレムがある。2001年には大林自動車の元社長を招聘してホンダコリアが設立され[24]、2004年に大林との提携を解消して「Honda」ブランドで韓国市場に直接参入するなど、1961年に韓国初のバイク「KIA Honda C100」を発売して以来、本田宗一郎の生前も没後もホンダと韓国の関わりは密接であり続けている。
また別の著書による社長退任のエピソードとして、エンジンを水冷か空冷かのどちらにするかという論争がホンダの中で巻き起こったころ、若い人は公害規制をクリアする意味で水冷だと主張したのに対し、本田は「砂漠の真ん中でエンストしたときに水なんかあるか!空冷だ」と主張したという。実際に一時は本田の意見が通りホンダ・1300の発売に至っているが、同時にこれは久米是志の出社拒否騒動に代表される若手エンジニアの反発を招いた(ホンダ・RA302およびホンダ・1300#本田宗一郎と空冷も参照のこと)。しかしさまざまなテストの結果、最終的に水冷の方が優れていることが分かり、ホンダは水冷エンジン路線に転換する。そのときに本田は「自分には技術が分からなくなったのかもしれない」と思い、社長を退いたという[25]。ホンダF1チーム監督であった中村良夫は、「結局、本田社長はもっとも基本的な熱力学の物理法則を理解していないので、いくらいっても論争がかみ合わないのです」「人間としては尊敬できるが技術者としては尊敬できない」と語っている。
「中村良夫 (自動車)」も参照
このほか、技術者としては2ストロークエンジンをあまり好まなかったことが伝えられる[26]。ホンダ・スーパーカブの開発時、当時は50ccエンジンであれば2ストロークが一般的だったところ、あえて4ストロークエンジンを開発し採用した[27]。
社長退職後、全国のHondaディーラー店を御礼参りする。その際、整備担当が握手を求めたが、自分の手が油だらけなことに気がつき、洗いに行こうとする。しかし、本田は自らも技術者であったため、油まみれの手での握手に喜んで応じた。[28]
意外に思われるが、岩倉信弥によれば高級品が大好きで、時計などはブランド品のいいものを好んでいたという。しかしこれは、「一流であるものを知っておく」という独自論からであり、実際に「ベンツのクオリティ並の軽自動車を作る」といったことも提言し、アコードとメルセデス・ベンツの乗り心地を技術者にドライブさせ比較検証するなどして実践していた。
逝去の2日前、さち夫人に「自分を背負って歩いてくれ」と言い、夫人は点滴の管をぶら下げた宗一郎を背負い病室の中を歩いた。そして「満足だった」という言葉を遺した。弔問時に遺族からそのエピソードを聞いた親友の井深大は「これが本田宗一郎の本質であったか」と述べ涙したという[29]。
その井深とは、ともに技術者出身でありシンパシーもあって、出会ってから自然と親友となった。そして、「互いの頼みごとは断らない」などのルールを決め、互いに文化事業などの役員を推薦し合って務めたという。また、互いに手紙をやり取りしあうことも忘れず、あるときに井深が「ワープロで手紙を送って、彼を驚かそう」と手紙を打っていたが、寸前に宗一郎が帰らぬ人となり、その手紙を送ることは叶わなかった[29]。
三ない運動に関して、「高校生から教育の名のもとにバイクを取り上げるのではなく、バイクに乗る際のルールや危険性を十分に教えていくのが学校教育ではないのか」と発言し、終始批判的なスタンスを取り続けた[30]。この考えはのちの本田首脳陣にも引き継がれ、徳島県の生光学園中学校・高等学校と共同実施する高校生への安全教習や、元会長の池忠彦による運動を推進する自治体への批判発言という形で具現化されている。
「自動車会社の創業者の自分が葬式を出して、大渋滞を起こしちゃ申し訳ない」という遺言を遺し、社葬は行われなかった。
■世界のオートバイ製造第1位のホンダと、同第2位のヤマハ発動機との間には深い因縁がある。第二次世界大戦当時、戦闘機用プロペラを製造する軍需工場となった日本楽器製造(現:ヤマハ)の社長であった川上嘉市は、金属加工技術に乏しく生産性が上がらない同社の状況に悩み、東海精機重工業(現:東海精機)の当時社長であった本田宗一郎を頼った。宗一郎はカッター式自動切削機を自作し、金属プロペラの製作時間はそれまでの一週間からわずか15分へと劇的に短縮された。嘉市は宗一郎を「日本のエジソン」と高く称賛し、特別顧問に迎えた[1]。
戦争終結後、オートバイ製造に転換したプロペラ工場は、ヤマハ発動機として産声を上げた。ここでも嘉市は助言を求め、宗一郎がこれに応える関係は続き、ヤマハ発動機創立に貢献した。当時、日本楽器製造は本社社長を兼ねる嘉市の長男・川上源一が就任していたが、彼は若い頃から常々宗一郎の高い能力を聞かされていたため異存を持たなかった。それどころか、1977年自らが会長に退くに当たり、当時のホンダ社長・河島喜好の実弟である河島博を日本楽器製造の専務から社長に昇格させ、後任に据えた。このような背景から、ホンダと日本楽器製造・ヤマハ発動機には地縁的同業という枠を越えた、一種の蜜月関係にあると業界は見ていた[2]。