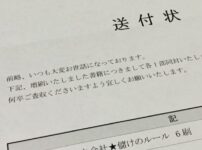約600pのノンフィクション読んだ感想「やっぱ身の丈以上の借金はダメだ(沢村でなく野口修)。借金は返さないといけない。返さず逃げたり隠れたりすれば、相手から一生恨まれる、陰口叩かれる、無視される(バブル時代5億資産プチ富裕栢野家は未亡人の母が連帯保証した浦川清史に1億やられて同時にバブル崩壊土地価格暴落自殺。お陰で少しはハングリーパワー身に付いた)。法的な破産や民事再生も平均9割以上踏み倒し。私は社長評論家30年やってるので、借金で倒産破産夜逃げ行方不明はたくさん観た。でも後で返済した人は表を歩ける。もしくは、借金1億に対して月に1万円でも返済し続けていれば=完済まで1000年でも、債権者の心情は良くなる。本人も「オレは返してる」と堂々と。はできないだろうが表は歩ける。まぁそうはいっても無理な人も多数。でも死ぬことはない。日本のど田舎か山谷西成、アジアへ高跳びしよう。フィリピンあたりにはワンサカいるはず。■KindleをiPadで読んだ。文字も大きく読みやすい。慣れたら■マスゴミや作家はペンで人を殺す非情な面も■大半の伝記自伝は良いとこだけのヨイショ本。本も著者も■人は誰でも良い表と黒い裏歴史がある。会社も商品も国も。真実を追求して表に出すと多くの人を傷つける。喜ばれることも■私は9冊経営本を実名事例で100人位取り上げたが、良いことのみ。中小無名個人は叩けない。悪徳詐欺は叩きのめす。
「キックボクシングを創った」※あとがき
「沢村忠を世に出した」
「五木ひろしを世に出した」
それらは、言われなくても知っていた。しかし、彼は繰り返し語った。「これを書き残してほしい」と哀願するようにも言った。
望みを叶えたいとは思ったが、旧来の通説に、証言を上書きしただけの本にするわけにいかない。そう決めた。※非情なマスゴミ
今にして思えばのことだが、そこから筆者は「時空旅行」に足を踏み入れたのかもしれない。永田町(国会図書館)に行けば、好きな時代に高跳びできた。仙台、新潟、横浜、横須賀、京都、奈良、大阪、神戸、広島、新居浜、バンコクへの取材も時空旅行だった。
筆者の関心は、常に野口修が生きた時代にあった。そこで得た情報を一つ一つ拾っては、現代に戻って本人にぶつけた。一見、気の遠くなる作業だが「旅行」と思えば、不思議と苦ではなかった。しかし、それはプロの仕事と言えるのかどうか。
取材時における野口修は、「そうそう」と感心したように相槌を打つこともあれば、「そんなこともあった」と懐かしんでみせたり、「どこでそれを知った」と気色ばむこともあった。
時には、野口修を時空旅行に巻き込むこともあった。
野口家の戸籍を閲覧するためには、文京区役所に行く必要がある。野口家の人間がいないと戸籍は取れない。筆者は、むずかる老人を区役所に連れて行った。強引すぎた気がしないでもない。思い出すと少し心が痛む。
しかし、そうして得た事実から認識したことは、彼は正真正銘、現代の格闘技ビジネスの源流に位置する人物であることだった。奇妙なのは、彼自身はそのことに、ほとんど無自覚だったことである。
そもそも、野口修は、事実を明かすことに消極的だった。今なら理由は判る。敗北や失敗をきっかけに、あらゆる物事がスタートしているからだ。本意ではなかったのだ。
家業のボクシングジムのマネージャーに収まったのも、「パスカル・ペレス対三迫仁志」の世界戦が、決まりそうで決まらなかったことに端を発する。本人はゼネコンの仕事に生き甲斐を見出しつつあった。
誰よりも早くタイというカードを握ったのも、三迫仁志がポーン・キングピッチに敗れたからだ。もし、このとき三迫が勝利を収めていれば、目論見通り、パスカル・ペレスの持つ世界フライ級王座に挑戦できた可能性は高いが、タイのボクシング界から厚遇されることは、おそらくなかっただろう。「タイ式ボクシング対大山道場」の対抗戦を企画したのも、外為法違反容疑で逮捕され、 NETのボクシング中継のプロモートから切られたからだ。
白羽秀樹という無名の青年を「沢村忠」に変身させたのも、キックボクシングの旗揚げ直前に、極真会館、日本拳法空手道という実戦空手の二大流派と仲違いしたことが背景にあった。もし、当初の望み通り、極真空手の中村忠をエースに船出していたら、キックボクシングは一体どうなっていたのか、どういうジャンルになったのか、皆目、見当がつかない。
芸能界に参入したのも、「姫」のママ、山口洋子と親密になりたかったからというのは、理由の一つとして否定できないのではないか。この時代の山口洋子の競争率は相当なもので、籠絡させたとあれば男として箔が付く。
身も蓋もないこれらの話を、本人の口から明かさせるのは酷だったかもしれない。
ただし、穿った見方をすれば、野口修本人が話したがらなかったからこそ、あらゆる事情が露顕したとも言える。あっけらかんと打ち明けていたら、筆者は重要な事象を見落としていたかもしれない。
手痛い失敗を成功に転化させた野口修は〝しくじり先生〟の元祖とも言うべき人物だった。「沢村忠」の名が躍る本書の表題だが、肝腎の表紙に沢村の姿はない。戸惑っている読者も多いかもしれない。
「それでも、裏方であるはずのプロモーターをあえて主人公に据えた本書の性格は、この表紙が最も的確に言い表している。それは、筆者が翻弄され続けた苦心の痕跡でもある。
激闘の末、日本王座を獲得した直後の弟、野口恭。勝利を称えるように、その手を挙げるプロモーターの兄、野口修。一見すれば、史上初の「親子日本王者」の快挙を成し遂げた野口恭にこそ、主役の称号を与えるべきだろう。
しかし、本木雅弘とも永瀬正敏ともつかぬ流麗な容貌と、屹立した佇まいの野口修には、裏方特有の薄暗さはまるでない。むしろ写真は、後年発せられる野口修の圧倒的な存在感を予期しているようでもある。筆者が、この写真を表紙に選んだ一番の理由はそこにあった。
本書の取材において、主人公の野口修以外にも多くの人物から話を聞いた。
最初に取材を申し込んだのは、意外なようだが、世界空手道連盟真樹道場を主宰した空手家にして、多くの著作をものしていた作家の真樹日佐夫だった。梶原一騎の実弟として知られる人物である。
筆者が以前、リングアナウンサーを務めていた M A日本キックボクシング連盟において、彼は最高相談役の任にあり、月に一度は必ず会場で顔を合わせていた。イベントの司会を任されたこともある。「野口さんの本? 面白そうだな。ただ、野口さんとは数回程度しか顔を合わせてない。兄貴は一時つるんでいたみたいだがな。まあ、知っていることは話してやる」
こうも言った。「ただ、沢村忠に話を聞かんわけにはいかんだろ。口を割らせることはできるか? ノンフィクションは裏取りと傍証が重要だから、時間はかかる。……いっそ、小説にしてみんか」 文人らしい教示は、筆者の現在までの遅滞を予見していたかのようでもある。
二〇一一年の師走のことである。 M A日本キックボクシング連盟の忘年会が開かれた。真樹日佐夫も、年内最終興行の直後とあって、指定された居酒屋に姿を見せた。
宴も一段落ついた頃、あるジムの会長が、酒の勢いも借りてかおもむろに立ち上がると、上座に陣取る真樹日佐夫にこう言い放った。「真樹先生、なんで今のキックは、こんなに食えないんですか。こんなに報われないのはどうしてですか。キックを全盛期のようにしたいです。選手をスターにしてやりたいですよ。
先生はその時代を知っている。先生のような重鎮のお力でテレビが付くようにして下さいよ。なんとかして下さいよ、先生」
真樹にとっていささか迷惑な直言に違いなかった。が、彼の主張にさほども批判の声があがらなかったのは、ジムの会長の多くが同様の苦しさに喘いでいたからだろう。
すると、真樹は気色ばむでもなく、しかし、発言の主を見据えてこう言った。「身も蓋もないことを言うようですまんが、往年のキックの全盛期というのは、沢村忠というスターを作り出せたから、客が来たし、テレビも乗っかったんだ。最初から恵まれた環境にあったわけじゃないんだよ。何もないところにテレビがあったわけでもない。そこを勘違いしてもらっては困る。
だから、君がそう望むなら、沢村に匹敵するスターを作りなさい。客を呼べる、テレビを呼べる、そういう選手を育てなさい。サボってはいかん。それをするのは、指導者たる君らの役目じゃあないか」
この回答は、結果として、一同に野口修の功績を暗に披歴したことになった。
忘年会から三週間後の二〇一二年一月二日、真樹日佐夫は、自身が愛した逗子のヨットハーバーで昏倒し、病院に搬送されたが、息を引き取った。七十一歳だった。
あの発言は、筆者にとって彼の遺言となった。 取材依頼は、当然のことだが、すべて快諾されたわけではない。
まず、野口修の遺族である。
父親が亡くなったことを、誰よりも早く筆者に報せてくれた長女だったが、その後は、まったく連絡が取れなくなった。人を介して「話を聞かせてほしい」と筆者は取材を申し込んだが、「父のことはよく知らないので」と一貫して断られた。
筆者が訊きたいのは「父のこと」ではなく、「父を見るあなたのこと」なのだが、彼女はそうは受け取らず、頑なにそう言い続けた。「訊かないで得られるものも、あるかもしれない」と、諦めることにした。
筆者はこれまで、二度、五木ひろしと会っている。
ただし、それはいずれも週刊誌の取材で、媒体は『週刊現代』( 2013年6月 14日号)と、『 FRIDAYダイナマイト』( 2017年5月 16日増刊号)である。『週刊現代』は、平尾昌晃、長沢純と往年を懐かしむ鼎談で、『 FRIDAYダイナマイト』は、芸能人の所属事務所の独立に関する特集だった。いずれも、野口プロモーションからの独立について、社長である野口修について現在の彼はどう思っているのかを知るいい機会だった。
取材前、五木自身は「なんでも話すよ」と言った。その言葉に偽りはなく、すべての質問に丁寧に答えてくれた。もちろん、記事の内容は抑制したものとはなったが、意外だった。
それもあって、本書の取材も応諾してくれるものと思ったが、現在の担当マネージャーからは、「書籍はちょっと……」と断られた。何度か頼んだが、無理だった。
しかし、取材時における彼の貴重な発言は、本書を著述する上で、重要な示唆にはなった。
遺族や五木ひろしですらそうなのだから、沢村忠については、推して知るべしである。
野口修を語る上で欠かせない沢村忠への取材を、どうにか実現できないものかと、筆者は終始、頭を悩ませてきた。「今も付き合いがある」と言う四人の人物に手紙を託した。しかし、いずれも彼らの口を通して拒まれた。手紙が本人の手に渡ったかどうかも疑わしい。
ある人物からは、沢村忠が役員として名を列ねていた関連企業の連絡先を聞いた。「私の名前を出してもらって構わない」と言う。すぐさま連絡を入れると「白羽は一年前に離職していまして」と女性の事務員に言われた。
ある人物は筆者を慰めるように言った。「引退してから、沢村さんは一切表に姿を見せなかったんだから仕方ない」 実際はそうではない。 九十年代に入ると、彼は『フルコンタクト KARATE』『ゴング格闘技』『 Sports Graphic Number』という三つの専門誌に登場している。カラーのページと特集記事、インタビューである。『ゴング格闘技』に至っては、 94年8月号で具志堅用高と対談を行い、 96年6月 8日号では「キックボクシング生誕」、、、
—『沢村忠に真空を飛ばせた男―昭和のプロモーター・野口修 評伝―』細田昌志著